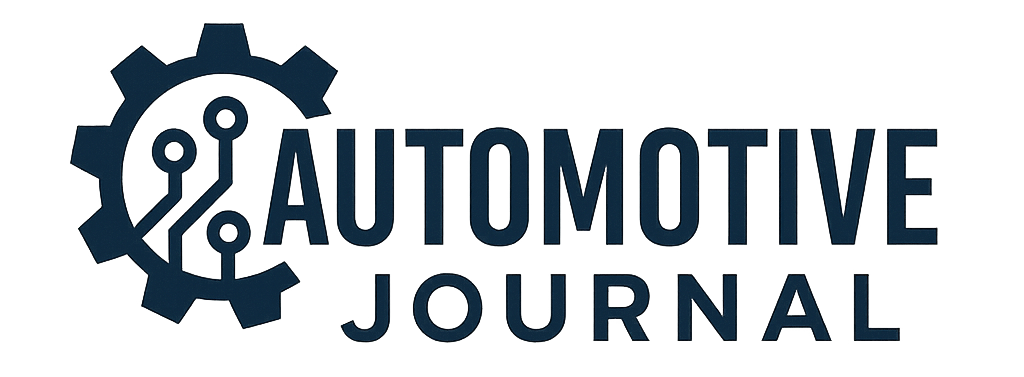原材料や労働コストだけでなく、バッテリーの大型化や高度な電子部品、巨額の研究開発費がEV価格を押し上げている。
EVの価格がなかなか下がらない理由は、原材料や労働コストだけではありません。最新技術の導入そのものがコスト増につながっているのです。
まず挙げられるのはバッテリーです。米欧の消費者は長距離走行を求める傾向が強く、平均で80kWh以上の大容量バッテリーを搭載する車種が主流となっています。これにより1台あたりのバッテリーコストは1万〜1万5千ドルに達し、車両価格の大きな部分を占めています。大きな電池は重量増も招くため、軽量化のためにアルミやカーボンファイバーといった高価な素材が多用されるのもコストを押し上げています。
さらに、EVには高性能なモーターやインバーター、バッテリー制御システムが欠かせません。シリコンカーバイドを使った高効率半導体や希土類磁石入りモーターなど、部品単価はガソリン車のエンジンより高い場合も少なくありません。また、先進運転支援システムや大型タッチスクリーン、常時接続のソフトウェア機能も「標準装備」として搭載されるケースが多く、開発やハードウェアにかかるコストが積み上がっています。
加えて、研究開発費の重さも無視できません。自動車各社は次世代電池やEV専用プラットフォーム、800V充電システムなどの開発に数十億ドル単位の投資を行っており、その費用は販売台数が限られる初期段階では1台ごとの価格に大きく反映されます。XPengのような中国メーカーも研究開発費を前年比5割増しで投じており、西側大手も同様に巨額投資を継続しています。つまり、現在のEV価格には「未来の低コスト化への先行投資」が含まれているのです。
さらに、急速充電や双方向充電、専用EVアーキテクチャなどの新技術を安全かつ量産レベルで統合するには膨大な検証と新しい設計が必要です。そのためガソリン車時代に可能だった部品の流用や設計の再利用が効きにくいという事情もあり、これが短期的なコスト高につながっています。
とはいえ、この状況は永続するわけではありません。リチウム鉄リン(LFP)電池の普及や「ギガキャスティング」などの生産革新によって、今後は1台あたりの製造コストが着実に下がっていく見通しです。現在の高価格は「技術革新期の宿命」であり、その投資が実を結ぶとき、大衆向けEVが本格的に普及する土台が整うといえるでしょう。
重要キーワード3つの解説
- 大容量バッテリー:長距離走行志向に応えるため大型化し、1万ドル以上のコスト要因となる。
- 高価な素材と部品:軽量化素材や先進半導体、希土類モーターが車両価格を押し上げる。
- 研究開発費の負担:新技術開発への巨額投資が、少ない販売台数に分散され高価格につながる。