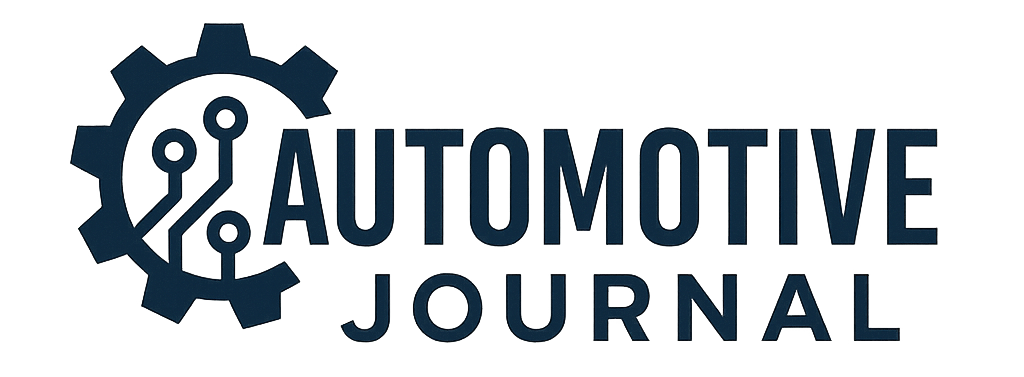ベンチャー企業の挑戦から始まる、一人乗りEVの普及とその未来
日本でも近年、街の移動を変える存在として超小型モビリティが注目を集めています。特に話題となっているのが、スタートアップや輸入企業による新しい一人乗り・二人乗りの超小型EVです。
広島県のKGモーターズは、一人乗り電動モビリティ「mibot(ミボット)」を開発中です。2024年夏に予約を開始すると、わずか1か月で1,000台超の予約が集まりました。その後も資金調達を進め、2025年には13.9億円の増資を実施し、量産体制の構築を急いでいます。mibotはエアコンやドアを備えた快適な一人乗りEVで、航続距離は約100km、最高速度は60km/h前後と日常の移動に十分な性能を持ち、2025年秋から本格的な生産が始まる予定です。
一方、輸入販売を手がけるアントレックス社は「EV-eCo」や「FAVICLE(ファビクル)」といった超小型EVを相次いで投入しています。EV-eCoは全長2.4m・重さ310kgとコンパクトながら、キャビンやバックモニターまで搭載。普通免許で運転でき、街中の短距離移動に適しています。さらに2025年7月からは三輪EV「FAVICLE」の出荷を開始しました。こちらは最大3人乗りで、一充電あたり110kmの走行が可能。通勤や送迎はもちろん、観光用モビリティとしても活用が期待されています。
政策面でも動きがあります。国のクリーンエネルギー自動車導入補助金では、一般的なEVに加え、小型・軽EVには最大58万円の補助が設定されています。これにより、個人だけでなく地方自治体や観光事業者の導入も進むとみられます。また、法制度の整備も進行中で、電動キックボードを含む「特定小型車両」制度の導入など、パーソナルモビリティ全体が広がりを見せています。
大手メーカーでは、トヨタが2人乗り超小型EV「C+pod」を展開していましたが、2024年夏に生産を終了。現在は日産の「サクラ」やホンダの次世代軽EVに注力しており、超小型EV分野はベンチャー企業が主導する展開となっています。今後、日本の都市や地方における「新しい足」として、こうしたモビリティがどこまで浸透するかが大きな注目点となるでしょう。
重要キーワード3つの解説
- 超小型モビリティ
軽自動車よりも小さな一人~二人乗りEVを中心とするカテゴリー。狭い道路や短距離移動に適し、高齢者や観光地での利用にも広がっている。 - mibot(ミボット)
KGモーターズが開発中の一人乗りEV。エアコン付きの快適なキャビンを持ち、都市部の「一人移動」を効率化する次世代モビリティとして期待される。 - EV-eCo / FAVICLE
アントレックス社が投入する輸入超小型EV。EV-eCoは都市型一人乗りEV、FAVICLEは三人乗りEVとして観光や送迎用途に広がりを狙う。