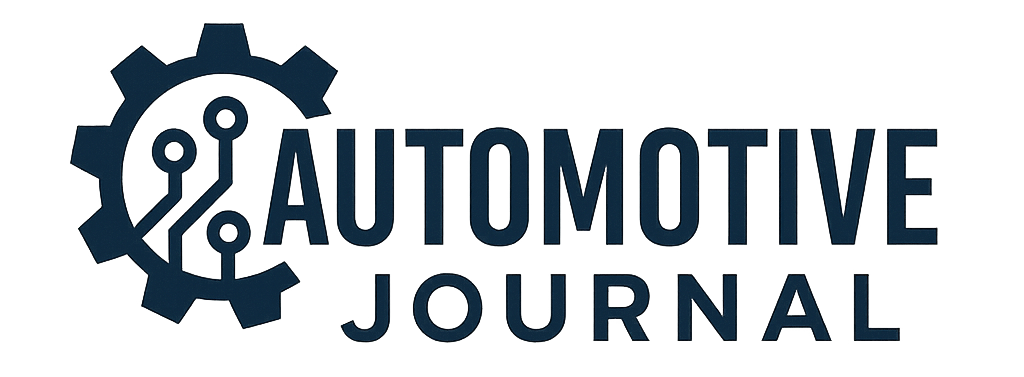- 欧米の厳格な規制に対し、対応が進む企業と遅れる企業の差が顕著に。
- 中国は目標超過の勢い、インドはまだ道半ば。
- トヨタやステランティスは、ロビー活動で規制後退を働きかける動きも。
ZEV規制の達成度とロビー活動の実態から見える、メーカーの本気度とリスク
ZEV(ゼロエミッション車)への移行は、各国の厳しいCO₂排出規制によって進められています。今回のICCT報告では、自動車メーカーが主要市場の規制にどれほど適応しているか、またその規制にどのような姿勢で関わっているか(ロビー活動)についても分析されました。
欧米市場:厳しい規制とギャップ
EUでは2025年までにEV比率36%が必要とされており、BMWやメルセデス、Geely傘下のボルボ等は既に達成。しかしトヨタ、ホンダ、日産など日本勢は大きく遅れを取っています。
米国では2027年に32%のEV比率が必要とされており、テスラがすでに基準を超え、BMWも健闘。対して、マツダ、トヨタ、ホンダなどはまだ10%未満にとどまり、追いつくには急速な転換が必要です。
中国・インド:異なるアプローチ
中国政府は2027年までにEV比率45%を目指していますが、2024年時点で既に44%に到達。BYD、Geely、SAICなどの中国メーカーやテスラは既にこの目標を超えました。
一方、インドは2030年までに30%という目標を掲げていますが、2024年の平均はわずか3%。現状ではSAICのみが達成済みで、Tata Motorsなども急ピッチで対応が必要です。
ロビー活動:賛成派と反対派
メーカーの規制に対する「本気度」はロビー活動からも見えてきます。InfluenceMapの評価(A+〜F)によると:
- BYD、Geely、Ford、GMなどは比較的規制支持の姿勢が強く、高評価(B〜Cクラス)
- トヨタは規制強化に反対し、D評価。米国やカナダ、英国でZEV規制緩和を働きかけていたと報告
- ステランティスは高いZEV目標を掲げつつも、米国EPAの新規制には冷淡な姿勢
今後の展開と懸念
ZEV規制は今後さらに厳格化され、2035年にはEUやカリフォルニア州で内燃機関車の新車販売が事実上禁止となります。現時点で規制未達のメーカーは、罰金やクレジット購入のコスト増リスクを抱えています。
一方、規制を上回る対応をする企業は、排出クレジットの販売収入でさらなる技術開発に再投資できる強みがあります。今後は、規制順守だけでなく、いかに積極的に未来の市場を創るかが問われる時代です。
重要キーワード3つの解説
- ZEV規制
各国が定めるゼロエミッション車(BEV、FCEV)の販売比率に関する義務。CO₂排出削減と産業政策の要。 - ロビー活動(Lobbying)
規制に対する企業の政治的働きかけ。支持・反対の姿勢が企業の戦略と透明性を示す。 - クレジット制度(Compliance Credits)
ZEV規制を超えた分を他社に販売できる制度。規制未達企業はこれを購入することで違反を回避する。
その他の記事
-
BMWとQualcommが共同開発、次世代自動運転「Snapdragon Ride Pilot」がついに始動
-
ついに上陸!MGの新ブランド「IM」が豪州に本格参入 ─ EV時代のプレミアムを再定義するIM5とIM6
-
BMW、第6世代電動パワートレイン(Gen6)を量産開始——800V技術と革新的制御でEV性能が大幅進化
-
BMW、新型電気モーターを本格生産開始 —— 800km走るiX3がいよいよ登場へ
-
規制とどう向き合う?自動車メーカーのZEV移行に対する姿勢を検証
-
テスラ、BYDが首位に君臨 日本勢は依然苦戦:2024年EV評価の全貌
-
EV化への本気度は?目標・投資・CEO報酬で分かるメーカーの覚悟
-
ドイツの自動車産業:革新と輸出を牽引する欧州のモビリティリーダー